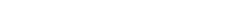- 産業用太陽光発電のメンテナンス費用が知りたい
- 今行ってるメンテナンスの費用が適正か知りたい
- メンテナンスの内訳や点検項目が知りたい
このような疑問にこの記事でお答えします。
メンテナンスはコスト増となり、売電収入を圧迫するためできれば避けたい・最小限にしたいとお思いの方もいるでしょう。
また、2017年の改正FIT法でメンテナンスが義務化もされ、適切な設備運用がされていない場合、最悪FIT認定の取り消しとなる事態になることも。
この記事では、産業用太陽光発電のメンテナンスにかかる費用を各メンテナンス項目別に解説すると共に、費用を最小限に抑えるポイントについても解説しています。
この記事を読めば一通りメンテナンスについての基本を抑え、売電収入を向上するのに必要な知識が得られます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
産業用・事業用太陽光発電のメンテナンス費用の相場
産業用・事業用の太陽光発電のメンテナンス費用の相場は、同じく「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」によると、0.4〜0.54万円/kW/年です。
実際は、産業用の太陽光発電は規模によってメンテナンス費用の相場が異なります。
ここでは50kW未満(低圧)・50kW以上(高圧)の2つに分けて両者を比較します。
低圧太陽光発電所(50kW未満)のメンテナンス費用は年間約10〜26万円
50kW未満の低圧の太陽光発電のメンテナンス費用は、年間約10〜26万円です。
「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」によると、10-50kWの事業用太陽光発電の運転維持費が
| 平均値 | 0.53万円/kW/年 |
| 中央値 | 0.4万円/kW/年 |
と記載されています。
例として49.5kWの発電所の場合に換算した場合、
平均値:0.53 * 49.5 = 26.235 万円
中央値:0.42 * 49.5 = 20.79 万円
となり、ここからおおよそ10〜26万円と見ていいでしょう。
もちろん各社の対応範囲や、どこまで業者に任せるかによっても変わってきます。
エナジービジョンでは、月額3,850円からメンテナンスを提供しています。詳しくは太陽光発電メンテナンス無料相談ページからご確認ください。
高圧太陽光発電所(50kW以上)のメンテナンス費用は 18.5〜1,580万円
50kW以上の高圧の太陽光発電のメンテナンス費用は、年間 18.5〜1,580万円前後が目安です。
kW数によってかなりの幅がありますが、「令和7年度以降の調達価格等に関する意見」では、
| 50-250kW | 250-500kW | 500-1,000kW | 1,000-2,000kW | 2,000kW以上 | |
| 平均値 (万円/kW/年) | 0.48 | 0.47 | 0.58 | 0.64 | 0.79 |
| 中央値 (万円/kW/年) | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.57 | 0.77 |
と記載されており、一番低い額と高い額でkW数を掛けて計算すると
0.37 * 50 = 18.5万円
0.79 * 2,000 = 1,580万円
になります。
高圧設備は発電規模が大きく、パネル枚数や電気設備も複雑なため、専門資格を持つ技術者による精密点検や高圧機器の管理が不可欠だからです。
さらに高圧発電所の場合は、電気事業法で以下の義務が発生します。
- 電気主任技術者の届出
- 保安規程を定め、管轄の産業保安監督部等への届出
- 第一種電気工事士による作業
メンテナンス頻度も届け出をした保安規定に則ってメンテナンス(多くは6ヶ月に1回以上の点検)をすることになります。
第一種電気工事士などの有資格者が必要になるため、専門の業者でないと対応できない検査項目も出てきます。
産業用太陽光発電のメンテナンス費用の内訳
メンテナンス費用はもちろん発電所の規模によっても変わってきます。
ここでは一般的に野立ての低圧発電所で多い構成である、パネル容量70kW、システム容量50kWの発電所の1区画あたりの料金で解説していきます。
以下で各内訳にかかるおおよその費用を表にまとめています。
| 電気的点検(精密点検) | 8万円 | |
| 目視点検 | 4万円 | |
| 雑草対策 | 草刈り | 7万円 |
| 除草剤散布 | 業者:5万円 自分で行う:2万8千円 | |
| 防草シート | 105万円 | |
| 駆けつけ対応 | 3万円 | |
| パワーコンディショナー修理 | 20〜40万円 | |
| パネル(太陽電池モジュール)の修理 | 7万円〜/1枚 | |
| フェンス・柵設置 | 7千円〜/1㎡ | |
| 保険・補償 | 賠償責任保険 | 7千円程度 |
| 売電補償 | 4万円程度 | |
| 火災保険 ※動産総合保険非加入の場合 | 12万円〜 | |
上の費用は一例です。実際は発電所の状況により大きく変わります
電気的点検(精密点検)にかかる費用
電気的点検でかかる費用の相場はおおよそ8万円前後です。
電気的点検では、
- 電気工事士等の有資格者が対応することが望ましい
- 現地に赴いて点検をする必要がある
- 各種専門機器を用いる必要がある
等の理由によって、メンテナンスの中でも高額な作業になります。
またインピーダンス測定、IVカーブ測定、EL検査など、どこまで深く電気的点検を行うかなどでも費用が変わってきます。
エナジービジョンでは、費用がかかる電気的点検の回数を減らしつつ発電量を維持するメンテナンスを提供しています。
また産業用太陽光発電全般のご相談も承っています。
現在無料相談キャンペーンを実施中ですので、お気軽にご相談ください。
目視点検にかかる費用
目視点検の費用相場は4万円前後となります。
先ほど説明したように、目視点検では目で見てわかる範囲の確認を中心に行います。
そのため有資格者でなくても対応できることもあり、電気的点検よりは安くなります。
またポイントを抑えれば、一般の発電事業者でも対応できるところでもあります。
雑草対策(除草)
雑草対策は除草方法によって費用が変わってきます。

奥山
一般的によく取られる雑草対策は主に草刈り、除草剤散布、防草シート、緑化植物によるカバーで、それぞれ費用が変わってきます。
以下それぞれの費用相場を紹介します。
草刈りにかかる費用
草刈りにかかる費用は7万円程度が多いかと思いますが、業者によってまちまちです。
発電所の近隣の業者に頼む方が、費用負担が少なく最も安くすみます。
また雑草の繁茂の状況によっても費用は大幅に変わります。
除草剤散布(土壌処理剤)にかかる費用
除草剤散布は、業者に頼むと5万円程度、除草剤を自分で購入し散布する場合は、除草剤の費用のみとなります。
1㎡あたり30gまくとして、700㎡であれば21,000g必要になるため、5kgのものであれば4袋が必要になります。
除草剤はだいたい5kgで7千円前後※の場合が多いため、合計2万8千円前後になります。
ただ除草剤の効果の持続は長くて6ヶ月程度のため、年間を通してまんべんなく撒くとすると、28,000 x2 = 56,000円前後かかることになります。
※除草剤の種類により金額は変わります
防草シートにかかる費用
防草シートを敷設する場合は、1㎡あたり300円〜1,500円前後の場合が多いです。
加えて敷設を業者に頼む際は、別途敷設費用もかかってきます。
700㎡の太陽光発電所の場合、高めの防草シートで700 x 1,500 = 1,050,000円(105万円)かかってきます。
安めの防草シートを選ぶと短期間で下からの草に突き破られたり、破損したりします。敷設し直しの必要が出てきて、結局高くついてしまいます。
防草シートを選ぶなら、10年以上持つしっかりとしたシートを選択することをおすすめします。
駆けつけ対応にかかる費用
緊急事態に現場への駆けつけ対応は3万円〜が相場です。
またパワーコンディショナーの故障、ケーブル切断などがあった場合には、別途修理・交換費用がかかります。
パワーコンディショナー故障の修理
パワーコンディショナーの修理・交換は工事費を含めて20万円〜40万円です。
パワーコンディショナーはメーカーの製品保証が5〜10年ついていることが一般的。
製造上の問題による不具合・故障に限り修理・交換をする保証です。
産業用太陽光発電の平均利回りは10%のため、投資回収するまでを考えると10年間の保証があると安心です。
オプションで保証を延長できる場合があるため、メーカーの製品保証が短い場合は問い合わせて確認するといいでしょう。
パネル・太陽光電池モジュールの故障の修理
太陽電池モジュールの修理・交換費用は1枚7万円〜が相場です。
太陽光パネル(太陽電池モジュール)はメーカーの製品保証が10〜15年ついていることが多いです。
パワーコンディショナーと同様に製造上の不備があった場合に限り、故障・不具合があった際に対応してもらえます。
太陽光パネルにおいてもメーカーの保証を延長できる場合があるため、メーカーの製品保証が短い場合は延長を検討してもいいでしょう。
フェンス・柵設置にかかる費用
フェンス・柵設置にかかる費用は、フェンスの種類にもよりますが1mあたり7千円~が相場です。
またフェンスの高さ、門扉をつけるか、基礎を設置するかでも変わってきます。
保険・補償
発電所で災害や損害が起こった時に、補償されるための保険にも加入します。
発電所を作った時に、販売店・施工店からおすすめされた保険に入ってる方が多いでしょう。
保険には大きく分けて動産総合保険または火災保険、賠償責任保険、売電補償(休業損害保険)の3種類の保険があります。
それぞれの保険の目的は以下の通り。
| 動産総合保険・火災保険 | 自然災害・盗難による被害に対する保険 |
| 賠償責任保険 | 第三者に損害を与えた場合の賠償責任に対する保険 |
| 売電補償(休業損害保険) | 自然災害等で発電が停止した際の売電収入の損失分を補償する保険 |
1年あたりの保険料は、施設賠償責任保険で約7千円、売電補償で約4万円が相場です。※
また動産総合保険が付帯していない場合は、自然災害などへの備えとして別途火災保険に入る必要があり、地域により異なりますが約12万円〜となります。
メーカー保証は製造に原因がある機器の不具合の対応のみなため、発電所運営のリスク対策として上記の保険で備える必要があります。
太陽電池モジュールの場合、メーカー保証の中には出力保証もあり、著しい発電量の下落に対して保証が効きます。
ただし、発電量が下落していることを見つけ、メーカーに保証請求するためのデータを揃える必要があります。
※低圧発電所の場合、
産業用太陽光発電のメンテナンス頻度
産業用太陽光発電所のメンテナンスの頻度としては、それぞれの点検項目や、どのような手法のメンテナンスを取るかで変わってきます。
頻度は主に現場での点検が必要な目視点検・電気的点検の頻度になりますが、2年に1回、また安めのプランであれば4年に1回のところが多いです。
また現場でのメンテナンスは目視・電気的点検に加えて、草刈り・除草剤散布など雑草対策も加わります。
草刈りであれば1年に2〜3回、除草剤散布も種類にもよりますが1年に2回は必要です。
パネル洗浄は発電量の低下傾向を把握して、必要であれば行えばいいでしょう。
エナジービジョンでは、人件費がかかる現場での点検回数を減らしつつ発電量を維持するメンテナンスを提供しています。
また産業用太陽光発電全般のご相談も承っています。
現在無料相談キャンペーンを実施中ですので、お気軽にご相談ください。
産業用太陽光発電(低圧)のメンテナンス費用を減らした成功事例3選
以下からはエナジービジョンにて行ったメンテナンスで、メンテナンス費用の削減に成功した事例を紹介します。
最低限のメンテナンスプランで53万円以上のメンテナンス費用削減。
1つ目はシステム容量49.5kWの産業用太陽光発電のメンテナンス費用を5年間合計で53万円削減した事例です。
以前のO&M会社のメンテナンス費用は年間15万円かかっていたところ、メンテナンスコストが安かったことを理由に弊社にメンテナンスを依頼いただきました。
エナジービジョンの5年契約のメンテナンスでは、「基本管理:3万円/年間」と「期間中に1回の電気的点検:7.2万円」。※
最低限の内容で5年間の合計費用が22.2万円(税別)です。
対して以前の会社は年間15万円だったため、5年間の合計は75万円。
そのまま以前の会社で継続していた場合と比べると、53万円のメンテナンス費用削減になっています。
エナジービジョンの独自の発電量解析を組み合わせ、発電量を維持しつつ現場での点検回数が減らせるため実現したメンテナンス費用削減です。
| 削減したメンテナンス費用 | 年間平均10.6万円、5年間53万円 |
| 発電所所在地 | 千葉県 |
| システム容量 | 49.5kW |
| 以前のメンテナンス費用(税別) | 150,000円/年間 |
| 切り替え後メンテナンス費用(税別) | 44,000円/年間 ※5年間の平均費用です |
初年度から11万円、5年間合計47.8万円のO&M費用削減
次に紹介するのは太陽光発電O&Mの費用を5年間合計で47.8万円減らせた事例です。
以前は発電所を購入した際に紐づいていた販売会社のメンテナンスを利用しており、年間24万円(税別)の費用がかかっていたとのこと。
当時の契約内容は、定期点検1回、パネル清掃1回、除草2回/年間の内容でした。
エナジービジョン社のメンテナンスプランに乗り換え後は、初年度の費用は、初回の現地調査1.5万円、基本管理3万円、年2回の除草作業8.5万円で、合計13万円。
初年度だけでも、11万円のO&M費用削減に成功しました。
4年目に7.2万円の電気的点検を予定しており、その電気的点検を足しても5年間合計72.2万円。
もともとの年間24万円から比べると、年間平均9.5万円、5年間で47.8万円のO&M費用削減に成功しています。
| 削減したメンテナンス費用 | 年間平均9.5万円、5年間47.8万円 |
| 発電所所在地 | 茨城県 |
| システム容量 | 49.5kW |
| 以前のメンテナンス費用(税別) | 240,000円/年間 |
| 切り替え後メンテナンス費用(税別) | 144,400円/年間 ※5年間の平均費用です |
※発電所によって初回の現地調査は必要ない場合もあり、さらに費用削減ができる場合もあります。
新メンテナンスプランへの切り替えで5年間で9.6万円の費用削減
3つ目に紹介するのは、弊社旧メンテナンスプランから「稼ぐ太陽光メンテ」へ移行して費用削減した事例です。
弊社の旧メンテナンスプランは、
- 電気的点検/年1回
- 設備補償
という内容で、費用は月額7,300円(税別)、年額87,600円(税別)でした。
契約更新のタイミングで「稼ぐ太陽光メンテ」へのプラン変更で、
- 基本管理
- 設備補償
上記の内容で、費用は年額54,000円(税別)。
毎年の電気的点検を省略することで、33,600円のO&M費用削減となりました。
4年に1回程度で7.2万円の電気的点検が入ってきますが、それも加味して5年間の合計金額で考えると、下記のとおりになります。
旧契約(低圧パックプラス) 毎年87,600円 × 5年間 =438,000円(税別)
新契約(稼ぐ太陽光メンテ) 毎年54,000円 × 5年間 + 7.2万円(4年に1度)=342,000円(税別)
5年間の合計額で見ると、96,000円のO&M費用削減となります。
太陽光発電の火災保険料が大幅に値上がりしている中、
設備補償も込みでメンテナンス費用を削減できるという点でもお客様に喜ばれました。
上記の通り弊社の旧プランをご契約いただいていたお客様であっても、発電事業者様のメリットになるのであれば、メンテナンス費用削減の提案をいたします。
| 削減したメンテナンス費用 | 年間平均1.92万円、5年間9.6万円 |
| 発電所所在地 | 茨城県 |
| システム容量 | 49.5kW |
| 以前のメンテナンス費用(税別) | 87,000円/年間 |
| 切り替え後メンテナンス費用(税別) | 68,400円/年間 ※5年間の平均費用です |
エナジービジョンで行っている発電量を維持して売電収入を減らすことなく、太陽光発電のメンテナンス費用を削減できる手法を紹介いたしました。
ご自分の太陽光発電のメンテナンス費用も減らせるか気になっている方はぜひお問い合わせください。
現在無料相談キャンペーンを実施中で、太陽光発電全般のご相談も承っています。
ぜひお気軽にご相談ください。
産業用太陽光発電のメンテナンス費用を最小限にするには

以下から産業用太陽光発電のメンテナンス費用を最小限にするポイントについて解説していきます。
自分でできる点検は自分で行う
産業用太陽光発電のメンテナンス費用を最小限に抑えるには、自分で行えるメンテナンスは自分で対応してしまうのが有効です。
ただ専門的な知識・技術を要する電気的点検については業者に任せることをおすすめします。
対して現場での目視点検は発電事業者でも取り組みやすいでしょう。
より詳しく知りたい方は、太陽光発電メンテナンスを自分で行う方法について解説した記事で紹介しています。合わせてご確認ください。
発電量を維持しつつ点検回数を極力減らす
産業用太陽光発電のメンテナンス費用を減らす際に気をつけたいのが、発電量を低下させないこと。
ずさんなメンテナンスで発電量が低下し、売電収入も低下してはメンテナンス費用を減らした意味がありません。
よって発電量を極力維持しつつ、メンテナンス費用を下げる必要があります。
エナジービジョンでは「発電量解析」という手法で発電量を維持しつつ、人件費がかかる電気的点検の回数を減らすことで発電量を維持しつつメンテナンス費用を削減しています。
かかるコストだけ見るのではなく、メンテナンス内容についてもしっかり確認するといいでしょう。
費用対効果を見て適切な除草を行う
太陽光発電で発電量を低下させる要因であり、費用がかかる主要な項目が雑草対策です。
雑草対策もただ漠然と草刈りをするのではなく、発電所の状況に合わせて適切な除草方法を選択することで費用削減につながります。
例えば毎年数回の草刈りを行うよりも、高品質な防草シートを敷いた方が長期間で見た場合トータルの費用負担が少なくなる場合もあります。
太陽光発電の雑草対策を解説した記事でも詳しく解説していますので参考にしてみてください。
産業用太陽光発電の点検項目は?
以下からは産業用太陽光発電のメンテナンス時の各点検項目について解説していきます。
まず太陽光発電事業に関して様々な取り決めを定めている、資源エネルギー庁の資料から確認しましょう。
「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」に沿った点検が求められる
改正FIT法では全発電事業者に「再生可能エネルギー発電事業計画書」の提出が義務付けられました。
この事業計画書作成において資源エネルギー庁の「事業計画策定ガイドライン」に従って適切に事業を行うことが記載されています。
「事業計画策定ガイドライン」には明確な基準は書かれていませんが、民間のガイドライン同等以上のメンテナンスを行うことと記載があります。
事業計画策定ガイドラインの付録参照に、一般社団法人太陽光発電協会から発行されている、「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」が推奨されています。
このガイドラインに沿ってメンテナンスを行うことで、前述の義務化の内容を守ることになると考えられているんですね。
以下、ガイドラインの内容と共に、特に代表的なメンテナンス・点検項目について紹介していきます。
産業用太陽光発電のメンテナンス・各点検項目の解説
産業用太陽光発電のメンテナンスは大きく分けて現地での点検と、遠隔での点検に分けられます。
定期点検
まずは現地での定期点検についてです。
電気的点検
電気的点検では専門機器を用いて、電気的故障がないか確認をします。
主に確認するのは、
- パワーコンディショナー
- 太陽電池モジュール
の2つです。
パワーコンディショナーについては、
- 絶縁抵抗
- 接地抵抗
等を点検します。
太陽電池モジュールについては、ストリングごとに、
- 開放電圧の測定
- 専門機器を使った抵抗値の測定
- サーモカメラによる確認
等が挙げられます。
電気的点検をすることで、発電所全体の電気的不具合がないか、またモジュール故障やストリングの断線がないか等の確認をします。
目視点検
目視点検においては主に、
- 地面の土砂流出・架台が傾いていないか
- 架台の破損、サビ・ネジの緩みがないか
- フェンスに破損がないか
- 太陽電池モジュールの焦げがないか
- ケーブル類が破損していないか
- 太陽電池モジュールがひどく汚れていないか
- 草木の影になっていないか
等を確認します。
特に架台・フェンスの破損、土砂流出、ボルトの緩みは遠隔監視では確認できないので目視での確認が必要です。
雑草対策
雑草対策では、太陽電池モジュールが草木の影にならないように対策を行います。
草刈り、除草剤、防草シートなどを用いて行いますが、適切な雑草対策は太陽光発電所の設置場所や状況によって変わります。
詳しくは太陽光発電の雑草対策を解説した記事を参考にしてみてください。
パネルの洗浄
パネル汚れの洗浄も行います。
野立ての太陽光発電所の場合、パネル角度が15度以上であれば大抵の汚れは雨で流されるため、頻繁な洗浄が必要なケースは少ないと思われます。
逆に、パネル角度が10度未満の場合などは、汚れが溜まって2、3年で発電量を大きく落としてしまうことがあります。
パネル洗浄は業者に頼むとそれなりに費用がかかるため、発電量の低下状況を把握して費用対効果を見て行うことをおすすめします。
また自分で洗浄する場合はモジュールを傷つけないようにすること、水道水を使う場合は拭き取ること、など注意が必要です。
監視業務
次に現場ではなく、遠隔での点検内容です。
アラート管理
監視システムを設置している場合、大幅な発電量の低下が起こるとアラート通知が来るようになっています。
このアラート通知が来た時に、監視システムで見ても不具合の原因がわからない場合や、現場での点検が必要な場合に駆けつけ対応を行います。
遠隔監視システムが備えているアラート管理による対応が一般的ですが、当社ではより高精度に実施するために「目付役」というシステムを開発・活用し、「日常監視」を提供しています。
「日常監視」では、遠隔監視システムの発電データを毎日確認し、PCSの停止など、大幅な発電低下を検知します。
不具合の原因が分からない場合に、一次対応として駆付け確認を行います。
遠隔監視
遠隔監視システムを用いて、発電量を監視します。
発電量の低下、パワーコンディショナーの低下などが起こった時に早期発見し、売電損失を防ぎます。
また不具合が発生した時に、いつから、どの部位に、どんな問題が発生しているのかを把握するために、遠隔監視システムのデータを用いて障害の切り分けを行います。
当社では遠隔監視システムの発電量データを解析して、中長期的な発電低下を検知する、「経年監視」を提供しています。
経年監視では主に、機器故障以外の緩やか、かつ、継続的な発電低下を見つけます。
不具合が発生した時に、いつから、どの部位に、どんな問題が発生しているか、経年監視の結果から推定し是正の方針を決める参考とします。
日常監視については、その精度にこだわらなければ対応しているメンテナンス業者も少なくありませんが、経年監視をサービス範囲内としている業者は、まだあまり多くありません。
エナジービジョンでは、「発電奉行」というシステムを開発・活用することで、経年監視を低コストで継続的に実現できる体制を実現しました。
今なら毎月限定20名様まで無料キャンペーン実施中。
発電量が落ちたままだと損失を出し続けることになります。
ぜひこの機会に発電力が少ない原因を特定し、損失を防ぎませんか?
駆けつけ対応
駆けつけ対応は、主に遠隔監視システムのアラートメールが来た際にデータを確認し、緊急性がある場合に現場に駆けつけ対応をするサービスです。
現場にて症状を確認し、復旧可能であれば復旧作業を行い、復旧が困難な場合は発電事業者との相談の上適切な対策を行います。
当社では、主に「日常監視」にて機器故障等の大きな発電低下を検知し、その原因が不明な場合に現場に駆けつけ一次対応をしています。
現場にて症状を確認し、復旧可能であれば復旧作業を行い、復旧が困難な場合は発電事業者と相談の上、適切な是正対応を行います。
フェンス・柵の設置
フェンス・柵の設置は改正FIT法でも義務付けられているため、対応が必須になります。
「事業計画策定ガイドライン」にフェンス・柵設置の5つの基準が定められており、基準に準ずる形での設置が必要です。
- フェンス・柵塀との設備の距離は外部から設備が触れられない程度にすること
- フェンス・柵塀の高さは、外部から容易に立ち入れられない高さにすること
- フェンス・柵塀の素材は、第三者が容易に取り除けないものにすること(ロープはNG)
- フェンス・柵塀の出入り口に施錠をし、容易に立ち入られないようにすること
- フェンスの外側の見えやすい場所に標識・立入禁止看板を掲示すること
以上の基準を満たすフェンス・柵を設置するようにしましょう。
以上が産業用太陽光発電のメンテナンス・点検項目です。
太陽光発電のメンテナンス・点検を自分で行う方法についても別記事で解説しているため合わせて参考にしてみてくださいね。
産業用太陽光発電にメンテナンスは必要?
そもそも産業用太陽光発電に本当にメンテナンスは必要なのか、疑問に思うかもしれません。
結論から申し上げると、産業用太陽光発電に適切なメンテナンスは必要不可欠です。
メンテナンスをしないことで、
- 機器の故障・草木の影・パネルの汚れ等で発電量が低下している
- ホットスポットによる火災等、事故リスクが高まる
等の理由により、売電損失を引き起こすことにつながります。
売電収入の低下・損失は発電事業者にとって死活問題ですよね。
以下詳しくメンテナンスの必要性について解説します。
発電効率を維持するため
産業用太陽光発電において、発電効率が下がることはそのまま発電量の低下につながります。
発電効率の低下は太陽電池モジュールの汚れ、パワーコンディショナー・モジュールの劣化・不具合、また草木の影がかかっている等、さまざまな要因によって引き起こされます。
メンテナンスをしていない場合、上記のような不具合・異常を発見するのが遅くなり、多額の売電損失を発生させる原因になります。
ケースによっては年間70万円もの売電損失が発生していた事例もあるほど。
発電効率を下げないためにも適切なメンテナンスが必要です。
※この記事では発電効率については簡易な説明に留めています。発電効率・変換効率について詳しく知りたい方は「太陽光発電の変換効率とは?発電量との関係を丁寧に解説(近日公開予定)」をご確認ください。
パワーコンディショナーの異常を検知するため
太陽光発電で一番故障率が高いのはパワーコンディショナーです。
パワーコンディショナーは電気に変換された直流電力を交流電力に変換し、送電する役割を担っています。
そのため、パワーコンディショナーが壊れると直ちに発電量に悪影響が出ます。
パワーコンディショナーは10〜15年が寿命と言われており、何もなく正常稼働していれば10年以上動き続けてくれます。
ただ寿命が切れる前でもゴミ・ホコリなどで換気フィルターが目詰まりを起こすことも。
また落雷の影響でパワコンの基盤が焦げてしまうこともあり得ます。
このように寿命が切れる前であったとしても、定期的にパワーコンディショナーの状態は確認する必要があります。
太陽光電池モジュール(太陽光パネル)の劣化を抑えるため
太陽光電池モジュールはパワーコンディショナーと比べると寿命が長いと言われていますが、それでも壊れる時は壊れるものです。
太陽光電池モジュールは一度悪化すると自然に直ることはありません。
最悪の場合、発火し火災を引き起こす可能性もあります。
モジュール自体の質によっても故障率は左右されます。
当然格安のモジュールの方が故障率は高くなるため、発電所建設時に安価なモジュールを選択した場合は注意が必要です。
上記のことから、今発電量が減少していないため不具合はない、と断定するのはリスクが高いです。
加えてモジュール表面の汚れも発電量を下げる原因となり、最終的にホットスポットの原因となることも。
モジュールにおけるメンテナンスは、
- 故障の確認
- 汚れの除去
- ホットスポットの有無の確認
が必要です。
またソラメンテZ等の専門的な測定機器でないと不具合の発見がしにくい、ということもあります。
太陽光パネル/ソーラーパネルと太陽電池モジュールはどちらも同じものを指しており、電気エネルギーを生み出す装置の名称です。
草木の影になる・汚れを防ぐため
野立ての太陽光発電所の場合、周囲が森や山に囲まれていて、草木が伸び影がかかってることもあります。
当然影がかかると発電量は低下するため、草刈り・防草シートなど雑草対策をした方がいいでしょう。
残念ながら、太陽電池モジュールは一部に影がかかるだけで、構造的にモジュールの1/3が発電しなくなることもあります。
発電量低下で収まる場合はまだいい方ですが、最悪の場合は発火する危険性も。
影がかかることで電気抵抗が上がってしまい、そこに無理に電流が流れホットスポットになり、燃えやすいものが触れて火災に至ります。
また先ほども解説した通り、モジュール上の汚れも発電量低下の原因となります。
架台やネジの緩みなどの不具合を防ぐため
架台自体がサビが発生していないか、ネジが緩んでいないかの確認も重要です。
サビは設備を朽ち果てさせ、強度を損ない倒壊のリスクを高めます。
サビを発見したら早めに適切な対策をするのが大切です。
また架台のネジが緩んでいないか、土台が沈んで傾いてる箇所がないかなど、基礎部分で不具合が発生していないかの確認もします。
改正FIT法のメンテナンスの義務に準ずるため
2017年に制定された「改正FIT法」でメンテナンスが義務化されてもいます。
義務化の背景として、
- 手入れされていない産業用太陽光発電所では電気事故が発生するリスクが増える
- メンテナンスされないまま放置(不法投棄)されてしまう
という事象が発生し、近隣住民から苦情も寄せられていました。
上記のような発電所をなくし、適切に管理された発電所のみにするため、改正FIT法が制定されました。
正確に言い表すと、この「義務」は「努力義務」とされており、必ずしも対応しなくてもよさそうに聞こえます。
しかし、この努力義務を怠っている場合はFIT制度認定取り消しの対象となるため、ほぼ対応必須ととらえていいでしょう。
太陽光発電の普及当初は、メンテナンスフリーと呼ばれた時代もありましたが、今や国も太陽光発電にメンテナンスは必要不可欠と考えていると言えます。
適切なメンテナンスをして太陽光発電所の資産価値を高めよう
以上のように、産業用太陽光発電において適切なメンテナンスは必要不可欠です。
しかし、産業用太陽光発電所は売電による投資目的で運用されているものが大半であり、費用対効果を見つつメンテナンスを行うことも重要です。
費用対効果を見るに当たって、行うメンテナンスがどれだけ売電収入に貢献するか、という視点で判断するといいでしょう。
売電収入は発電量に直結します。
つまりは「得られる発電量」と、「発電量を維持するためのメンテナンスコスト」を照らし合わせて判断するのが理想です。
エナジービジョンでは、「元の発電量がどれだけ維持できているか」を見る「発電量解析」を行い、メンテナンス費用負担を最小限に抑えつつ発電量をアップさせるメンテナンスサービスを提供しています。
さらに産業用太陽光発電所について相談できる無料相談会も受付中。
以下のリンクからお申し込みいただけます。